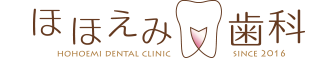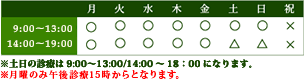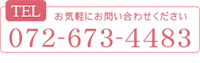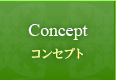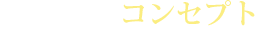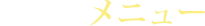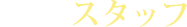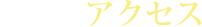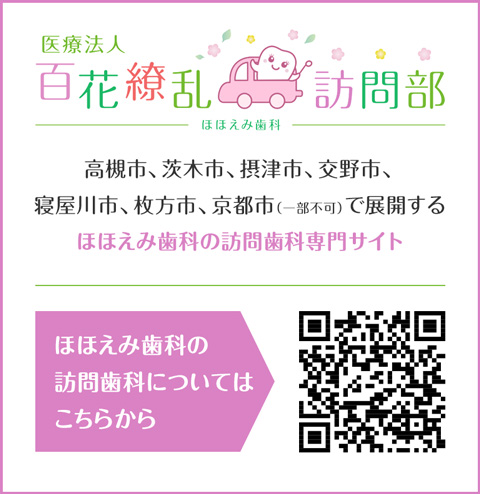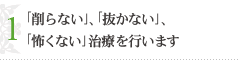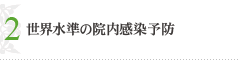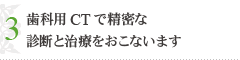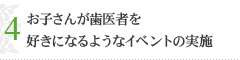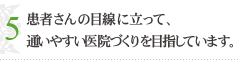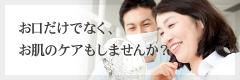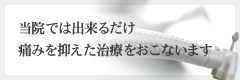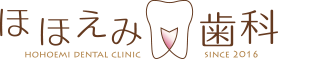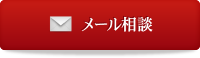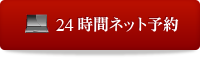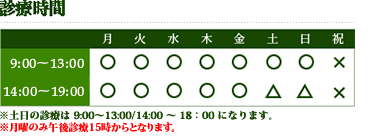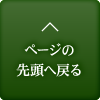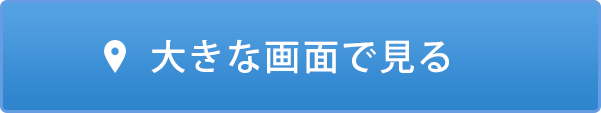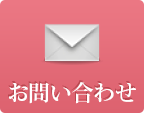歯周病が引き起こす全身疾患
こんにちは!ほほえみ歯科です!

歯周病が引き起こす全身疾患
はじめに
歯周病は単なる口腔内の問題ではなく、全身の健康に影響を及ぼす重大な疾患として認識されるようになってきました。歯周病は歯茎の炎症から始まり、進行すると歯を支える組織や骨の破壊につながります。日本では成人の約80%が何らかの歯周病に罹患していると言われており、国民病とも呼ばれています。しかし、その危険性は口腔内にとどまらず、全身の様々な疾患との関連性が科学的に証明されつつあります。
歯周病菌や炎症性物質が血流に乗って全身に広がることで、遠隔臓器にも影響を及ぼすという「口腔感染巣説」は、現代の医学で広く受け入れられています。本稿では、歯周病と全身疾患との関連性について詳しく解説し、口腔ケアの重要性について再考します。
歯周病の基礎知識
歯周病は歯と歯茎の間の歯周ポケットに細菌が蓄積することで発症します。初期段階の歯肉炎では、歯茎の赤み、腫れ、出血などの症状が現れますが、適切なケアで回復可能です。しかし放置すると、歯周炎へと進行し、歯を支える組織や骨が破壊され、最終的には歯の喪失につながります。
歯周病の主な原因は歯垢(プラーク)の蓄積ですが、喫煙、ストレス、糖尿病、ホルモンバランスの変化なども発症リスクを高めます。また、遺伝的要因も歯周病の感受性に影響を与えると考えられています。
歯周病菌は口腔内に700種類以上存在するとされ、代表的なものにはPorphyromonas gingivalis(P.g菌)、Aggregatibacter actinomycetemcomitans(A.a菌)、Treponema denticola(T.d菌)などがあります。これらの菌は歯周ポケット内で増殖し、毒素を産生することで炎症反応を引き起こします。
歯周病と心血管疾患
歯周病と心血管疾患との関連性は数多くの研究で指摘されています。特に、冠動脈疾患や脳卒中のリスクが歯周病患者で高まることが報告されています。
歯周病菌が血流に入ると、動脈壁に付着して炎症を引き起こし、動脈硬化のプロセスを促進すると考えられています。実際、動脈硬化プラークから歯周病菌のDNAが検出されたという報告もあります。また、歯周病による慢性炎症は、CRP(C反応性タンパク)などの炎症マーカーの上昇を引き起こし、これが心血管疾患のリスク因子となります。
アメリカ心臓協会(AHA)の研究では、歯周病治療によって血管内皮機能が改善し、炎症マーカーの減少が見られたと報告されています。また、歯周病治療を受けた患者は将来的な心血管イベントのリスクが低下するという長期観察研究の結果も発表されています。
歯周病と糖尿病
歯周病と糖尿病は双方向性の関係にあります。糖尿病患者は歯周病のリスクが約3倍高くなるとされ、一方で重度の歯周病は血糖コントロールを悪化させることが知られています。
歯周病による慢性炎症は、インスリン抵抗性を高めるTNF-α(腫瘍壊死因子アルファ)やIL-6(インターロイキン6)などの炎症性サイトカインの産生を増加させます。これにより、糖尿病患者の血糖コントロールが困難になり、合併症のリスクが高まります。
一方、適切な歯周病治療を行うことで、HbA1c(ヘモグロビンA1c)値の改善が見られるという研究結果も多数報告されています。日本糖尿病学会のガイドラインでも、糖尿病患者への歯周病スクリーニングと治療の重要性が強調されています。
歯周病と呼吸器疾患
口腔内の細菌が気道に吸引されることで、肺炎などの呼吸器感染症を引き起こす可能性があります。特に高齢者や免疫機能が低下している患者では、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。
歯周病菌を含む口腔内細菌が呼吸器系に感染すると、直接的な感染源となるだけでなく、呼吸器系の粘膜表面に定着して宿主の防御機能を変化させ、病原体の付着と定着を促進することがあります。また、歯周病による炎症性サイトカインの増加は、全身の炎症レベルを上昇させ、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの慢性呼吸器疾患の進行を加速させる可能性があります。
介護施設や病院での口腔ケアプログラムの導入により、高齢者の肺炎発症率や肺炎による死亡率が有意に減少したという報告もあります。
歯周病と妊娠への影響
妊娠中の女性が歯周病に罹患していると、早産や低出生体重児のリスクが高まることが報告されています。これは歯周病菌や炎症性物質が胎盤を通じて胎児に影響を与えるためと考えられています。
歯周病による炎症は、プロスタグランジンE2(PGE2)などの物質の産生を増加させ、これが子宮収縮を促進して早産を引き起こす可能性があります。また、歯周病菌の一部は胎盤や羊水から検出されることがあり、子宮内感染のリスクも懸念されています。
妊娠前や妊娠初期に歯周病治療を行うことで、早産や低出生体重児のリスクを低減できるという研究結果も報告されています。日本産科婦人科学会でも、妊婦健診における歯科検診の重要性が強調されています。
歯周病と関節リウマチ
歯周病と関節リウマチは共通の病態メカニズムを持つことが示唆されています。両疾患とも慢性炎症性疾患であり、TNF-αなどの炎症性サイトカインが重要な役割を果たしています。
特に注目されているのは、P.g菌の産生する酵素ペプチジルアルギニンデイミナーゼ(PAD)です。この酵素はタンパク質のシトルリン化を引き起こし、関節リウマチの自己抗体である抗シトルリン化タンパク抗体(ACPA)の産生を促進する可能性があります。
複数の研究で、関節リウマチ患者は歯周病の有病率が高く、逆に重度の歯周病患者は関節リウマチを発症するリスクが高いことが報告されています。また、歯周病治療によって関節リウマチの症状が改善するケースも観察されています。
歯周病とアルツハイマー病
近年、歯周病とアルツハイマー病を含む認知症との関連性についても注目されています。歯周病菌が血液脳関門を通過して脳内に侵入し、神経細胞の変性や炎症を引き起こす可能性が指摘されています。
特にP.g菌はアルツハイマー病患者の脳組織から検出されることがあり、アミロイドβの蓄積やタウタンパクのリン酸化を促進するという実験結果も報告されています。また、歯の喪失数と認知機能低下には相関関係があるという疫学研究もあります。
口腔ケアの改善や歯周病治療によって認知機能の低下を予防できる可能性が示唆されており、高齢化社会における新たな認知症予防戦略として注目されています。
歯周病と癌
歯周病と特定の癌、特に口腔癌、食道癌、膵臓癌などとの関連性も報告されています。慢性炎症は発癌プロセスを促進することが知られており、歯周病による長期的な炎症状態が癌のリスクを高める可能性があります。
歯周病菌の一部は細胞の遺伝子発現を変化させたり、発癌物質を産生したりする能力を持つと考えられています。また、歯周病菌による慢性炎症は、DNAの損傷や細胞の増殖、血管新生などを促進し、腫瘍の発生や進展に寄与する可能性があります。
長期観察研究では、重度の歯周病患者は全体的な癌発症リスクが約24%増加するという結果も報告されています。
予防と対策
歯周病と全身疾患の関連性を考えると、口腔ケアは全身の健康維持に不可欠です。以下のような予防策が推奨されます:
- 徹底した口腔清掃: 正しい歯磨き、フロス、歯間ブラシの使用
- 定期的な歯科検診: 最低でも年に2回の専門的クリーニングと検査
- 早期治療: 歯肉の出血や腫れなどの症状が現れたら早めに歯科医院を受診
- 禁煙: 喫煙は歯周病の主要なリスク因子であり、治療効果も減弱させる
- バランスの良い食事: 抗酸化物質やビタミンCなど、歯周組織の健康に必要な栄養素の摂取
- ストレス管理: 過度のストレスは免疫機能に影響し、歯周病のリスクを高める
特に全身疾患のリスクがある方や、すでに慢性疾患を抱えている方は、医科と歯科の連携治療(医歯連携)が重要です。例えば、糖尿病患者は定期的な歯科受診を習慣化し、歯周病の早期発見・早期治療を心がけるべきです。
おわりに
歯周病は「サイレントキラー」とも呼ばれ、初期段階では自覚症状が乏しいために見過ごされがちです。しかし、その影響は口腔内にとどまらず、全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
現代医学では、口腔の健康と全身の健康は密接に関連しているという「オーラルヘルスとシステミックヘルスの統合」という概念が広まりつつあります。歯科医療は単に歯を治すだけでなく、全身の健康維持に貢献する予防医学の一環として捉えられるようになってきました。
経験豊富な専門医による怖くない安心のおすすめインプラント治療、高槻市ほほえみ歯科で理想の笑顔を手に入れましょう!
是非、ご来院ください。