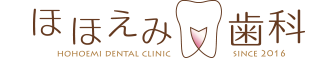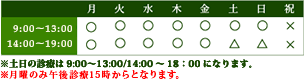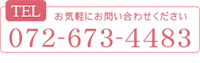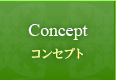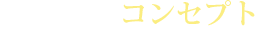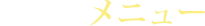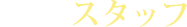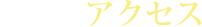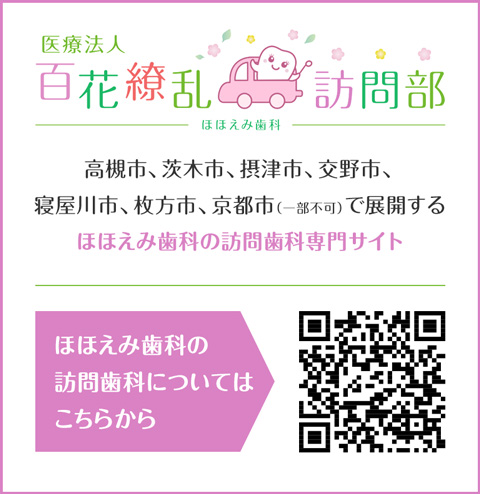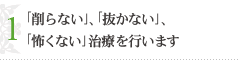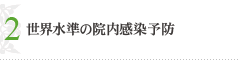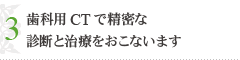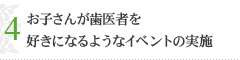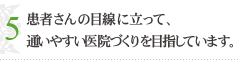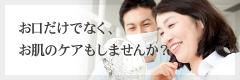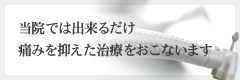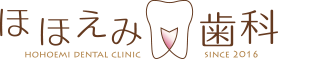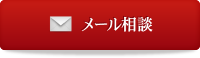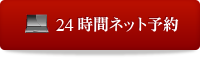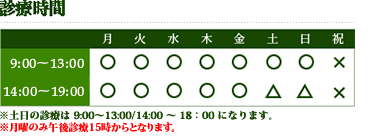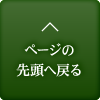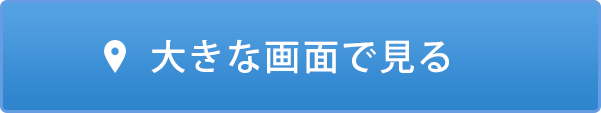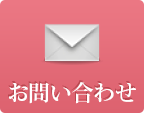虫歯になりやすい歯・なりにくい歯の違いとは?
虫歯になりやすい歯・なりにくい歯の違いとは?

同じ口の中にあるのに、なぜ特定の歯だけ虫歯になりやすいのでしょうか。この疑問を持ったことがある方は多いはずです。実は、虫歯のリスクは歯の位置や形状、個人の生活習慣によって大きく異なります。虫歯になりやすい歯となりにくい歯の違いを理解することで、より効果的な予防対策を立てることができるでしょう。
虫歯になりやすい歯の特徴
奥歯(大臼歯・小臼歯)
奥歯は虫歯になりやすい歯の代表格です。その理由は複数あります。まず、奥歯の咬合面には深い溝があり、食べカスや細菌が蓄積しやすい構造になっています。これらの溝は「小窩裂溝」と呼ばれ、歯ブラシの毛先が届きにくく、清掃が困難な部位です。
また、奥歯は口の奥に位置するため、歯磨きの際に十分にブラシが届かないことが多く、プラークが残りやすくなります。特に親知らずは最も奥に位置するため、清掃が最も困難で、虫歯のリスクが非常に高い歯として知られています。
歯と歯の間(隣接面)
隣接面虫歯は見た目では発見しにくく、進行してから気づくことが多い虫歯です。歯と歯の間は唾液の自浄作用が働きにくく、食べカスや細菌が停滞しやすい環境にあります。特に歯並びが悪く、歯が重なっている部分では、この傾向がより顕著になります。
デンタルフロスや歯間ブラシを使用しない限り、この部位の清掃は不十分になりがちです。そのため、日常的に歯間清掃を行っていない人では、隣接面虫歯のリスクが大幅に上昇します。
歯頸部(歯の根元)
歯頸部は歯と歯茎の境界部分で、年齢とともに歯茎が下がることで露出しやすくなります。この部位のエナメル質は薄く、象牙質が露出している場合もあるため、酸に対する抵抗力が弱く、虫歯になりやすい特徴があります。
また、歯頸部は歯ブラシが当たりにくい角度にあるため、プラークが蓄積しやすく、清掃が困難な部位でもあります。特に加齢とともに唾液の分泌量が減少すると、この部位の虫歯リスクはさらに高まります。
虫歯になりにくい歯の特徴
前歯(切歯・犬歯)
前歯は比較的虫歯になりにくい歯です。その理由として、まず形状が単純で表面が滑らかなため、プラークが付着しにくいことが挙げられます。また、前歯は唾液腺に近い位置にあるため、唾液による自浄作用や再石灰化作用を十分に受けることができます。
さらに、前歯は歯磨きの際にアクセスしやすく、日常的な清掃が比較的容易です。特に下の前歯は唾液腺の開口部に最も近いため、常に豊富な唾液に晒されており、虫歯になりにくい環境にあります。
犬歯の特別な性質
犬歯は前歯の中でも特に虫歯になりにくい歯として知られています。犬歯は根が長く、歯冠の形状もシンプルで、プラークが付着しにくい構造になっています。また、犬歯は咬合時に他の歯を保護する役割を果たしており、その機能的な重要性から、進化的に虫歯に対する抵抗力が高くなったと考えられています。
個人差による虫歯リスクの違い
唾液の質と量
唾液は虫歯予防において極めて重要な役割を果たします。唾液の分泌量が多い人は、口腔内の細菌や酸を洗い流す自浄作用が強く、虫歯になりにくい傾向があります。また、唾液に含まれるカルシウムやリンなどのミネラルは、歯の再石灰化を促進し、初期虫歯の修復に貢献します。
唾液のpH値も重要な要素です。通常の唾液は弱アルカリ性で、酸性に傾いた口腔内環境を中和する働きがあります。しかし、ストレスや薬物の副作用、加齢などにより唾液の分泌量が減少したり、pH値が変化したりすると、虫歯のリスクが高まります。
歯の質とエナメル質の厚さ
歯の質には個人差があり、エナメル質の厚さや密度、フッ素の含有量などが虫歯の抵抗力に大きく影響します。エナメル質が厚く、結晶構造が緻密な歯は、酸に対する抵抗力が高く、虫歯になりにくい特徴があります。
また、幼少期にフッ素入りの歯磨き粉を使用していた人や、フッ素塗布を受けた経験がある人は、歯質が強化されており、虫歯になりにくい傾向があります。
口腔内細菌叢の違い
口腔内には数百種類の細菌が存在し、その構成は個人によって大きく異なります。虫歯の原因となるミュータンス菌の数が多い人は、当然ながら虫歯になりやすくなります。一方、有益な細菌が優勢な口腔内環境を持つ人は、虫歯菌の活動が抑制され、虫歯になりにくい状態を保つことができます。
生活習慣による虫歯リスクの変化
食事習慣の影響
糖分を多く含む食品や飲料を頻繁に摂取する人は、虫歯菌の活動が活発になり、虫歯のリスクが高まります。特に、間食の回数が多い人や、糖分を含む飲み物を長時間かけて飲む習慣がある人は要注意です。
逆に、繊維質の多い食品を積極的に摂取し、よく噛んで食べる習慣がある人は、唾液の分泌が促進され、自然な口腔清掃効果が得られます。
口腔ケア習慣
当然ながら、適切な口腔ケアを行っている人は虫歯になりにくくなります。正しい歯磨き方法を実践し、フロスや歯間ブラシを使用して歯間清掃を行い、定期的に歯科検診を受けている人は、虫歯のリスクを大幅に減らすことができます。
虫歯予防のための戦略
個人の特性に応じた予防法
自分の口腔内の特徴を理解し、それに応じた予防策を立てることが重要です。奥歯に虫歯ができやすい人は、シーラント処置を検討したり、奥歯の清掃により時間をかけたりする必要があります。
隣接面虫歯のリスクが高い人は、必ずデンタルフロスや歯間ブラシを使用し、定期的な歯科検診で早期発見に努めることが大切です。
総合的なアプローチ
虫歯予防は単一の方法では効果が限定的です。適切な口腔ケア、バランスの取れた食事、定期的な歯科受診を組み合わせた総合的なアプローチが最も効果的です。
また、年齢や生活環境の変化に応じて、予防方法も調整していく必要があります。例えば、加齢とともに唾液分泌量が減少する場合は、より頻繁な水分摂取や人工唾液の使用を検討することも重要です。
まとめ
虫歯になりやすい歯となりにくい歯の違いは、歯の位置、形状、個人の体質、生活習慣など複数の要因によって決まります。この違いを理解することで、より効果的で個人に適した虫歯予防策を立てることができます。重要なのは、自分の口腔内の特徴を把握し、それに応じたケアを継続することです。定期的な歯科検診を受けながら、生涯にわたって健康な歯を維持していきましょう。
治療内容をしっかりとご説明し、納得して頂くことで怖くない歯科医院を目指します!
高槻市おすすめ、ほほえみ歯科、是非ご来院ください。